数理的デッキ構築理論と4cドラゴンにおける実践
2016年2月9日定理
ある種類のカードについて、先攻Xターン目までにちょうどY枚引く確率を最大化する(=Xターン目までにのドローする枚数の期待値をYにする)投入枚数は次式となる。
(デッキ枚数)×Y/(X+6)枚
概論
最低N枚引く確率やaとbを同時に引く確率などを考慮し採用枚数を決定するのは計算が煩雑かつ、実際のデッキ構築に反映させるのが難しい。デッキ構築に求められるのは勝率の最大化であるから、概算のためには上記の式で十分である。
2つの変数のみでデッキ投入枚数が即求まるのは大きな利点である。試行結果やメタゲームをフィードバックするのが簡便であり、目的に応じXまたはYを増減させれば良い。
数値に基づくため、少ない試行回数の印象に引きずられ調整を誤ることが少ない。
実践
この理論に基づき、実際に4cドラゴンの調整を行った。
クリーチャー
5ターン目までに2枚→2/11→11枚
うちドラゴン
7ターン目までに1枚→1/13→4.5枚
包囲サイ 4
雷破の執政 4
闇住まい 3
土地
5ターン目まで5枚→5/11→28枚
2枚をムラーサの胎動にしてフラッドを緩和する。
1〜2マナ除去・ハンデス
初手に1枚→1/7→9枚
強迫 2
咆哮 4
炙り焼き 2
ショック 1
3マナ除去
3ターン目までに1枚→1/9→7枚
はじける破滅 4
アブザンチャーム 3
残り自由枠 5枚
コラコマ2
タシグル2
疾駆コラガン1
理論の適用に際しての注意点はカードの分類を細分化しすぎない事である。細分化されてしまうのはデッキのコンセプトが定まっておらず採用カードの方向性が一致していないからである。
サイドボードを調整する際にも適用できる。想定するマッチアップ毎にメインボード+サイドボードの有効カード枚数をカウントし、何ターン目までに何枚引きたいのかを考えればよい。計算は単純なため構築だけではなく柔軟なサイドボーディングの助けにもなるだろう。
完成したデッキ
1:《嵐の憤怒、コラガン/Kolaghan, the Storm’s Fury》
4:《雷破の執政/Thunderbreak Regent》
4:《包囲サイ/Siege Rhino》
2:《黄金牙、タシグル/Tasigur, the Golden Fang》
3:《ゴブリンの闇住まい/Goblin Dark-Dwellers》
2:《ムラーサの胎動/Pulse of Murasa》
2:《焙り焼き/Roast》
3:《アブザンの魔除け/Abzan Charm》
2:《コラガンの命令/Kolaghan’s Command》
4:《はじける破滅/Crackling Doom》
4:《龍詞の咆哮/Draconic Roar》
2:《強迫/Duress》
1:《乱撃斬/Wild Slash》
1:《梢の眺望/Canopy Vista》
1:《燃えがらの林間地/Cinder Glade》
4:《血染めのぬかるみ/Bloodstained Mire》
3:《乱脈な気孔/Shambling Vent》
1:《燻る湿地/Smoldering Marsh》
4:《樹木茂る山麓/Wooded Foothills》
2:《吹きさらしの荒野/Windswept Heath》
1:《平地/Plains》
1:《沼/Swamp》
2:《山/Mountain》
2:《森/Forest》
2:《砂草原の城塞/Sandsteppe Citadel》
2:《遊牧民の前哨地/Nomad Outpost》
サイドボード
2:《神聖なる月光/Hallowed Moonlight》
1:《苦い真理/Painful Truths》
2:《強迫/Duress》
1:《黄金牙、タシグル/Tasigur, the Golden Fang》
1:《悪性の疫病/Virulent Plague》
2:《精神背信/Transgress the Mind》
1:《魂火の大導師/Soulfire Grand Master》
2:《光輝の炎/Radiant Flames》
1:《焙り焼き/Roast》
1:《乱撃斬/Wild Slash》
1:《炎駆の乗り手/Flamerush Rider》
実験結果
トナプラ
マルドゥメンター ○○
2構
アブザンエルドラージ ○○
青白トークン ×× 反射魔道士でブロッカー突破 ロックでダメージレース不可
8構
ブルーアブザン ○×○ アナフェンザから反射魔道士
4cラリー ○○
アブザンアグロ ○○
提案法の有効性が示唆された。
ある種類のカードについて、先攻Xターン目までにちょうどY枚引く確率を最大化する(=Xターン目までにのドローする枚数の期待値をYにする)投入枚数は次式となる。
(デッキ枚数)×Y/(X+6)枚
概論
最低N枚引く確率やaとbを同時に引く確率などを考慮し採用枚数を決定するのは計算が煩雑かつ、実際のデッキ構築に反映させるのが難しい。デッキ構築に求められるのは勝率の最大化であるから、概算のためには上記の式で十分である。
2つの変数のみでデッキ投入枚数が即求まるのは大きな利点である。試行結果やメタゲームをフィードバックするのが簡便であり、目的に応じXまたはYを増減させれば良い。
数値に基づくため、少ない試行回数の印象に引きずられ調整を誤ることが少ない。
実践
この理論に基づき、実際に4cドラゴンの調整を行った。
クリーチャー
5ターン目までに2枚→2/11→11枚
うちドラゴン
7ターン目までに1枚→1/13→4.5枚
包囲サイ 4
雷破の執政 4
闇住まい 3
土地
5ターン目まで5枚→5/11→28枚
2枚をムラーサの胎動にしてフラッドを緩和する。
1〜2マナ除去・ハンデス
初手に1枚→1/7→9枚
強迫 2
咆哮 4
炙り焼き 2
ショック 1
3マナ除去
3ターン目までに1枚→1/9→7枚
はじける破滅 4
アブザンチャーム 3
残り自由枠 5枚
コラコマ2
タシグル2
疾駆コラガン1
理論の適用に際しての注意点はカードの分類を細分化しすぎない事である。細分化されてしまうのはデッキのコンセプトが定まっておらず採用カードの方向性が一致していないからである。
サイドボードを調整する際にも適用できる。想定するマッチアップ毎にメインボード+サイドボードの有効カード枚数をカウントし、何ターン目までに何枚引きたいのかを考えればよい。計算は単純なため構築だけではなく柔軟なサイドボーディングの助けにもなるだろう。
完成したデッキ
1:《嵐の憤怒、コラガン/Kolaghan, the Storm’s Fury》
4:《雷破の執政/Thunderbreak Regent》
4:《包囲サイ/Siege Rhino》
2:《黄金牙、タシグル/Tasigur, the Golden Fang》
3:《ゴブリンの闇住まい/Goblin Dark-Dwellers》
2:《ムラーサの胎動/Pulse of Murasa》
2:《焙り焼き/Roast》
3:《アブザンの魔除け/Abzan Charm》
2:《コラガンの命令/Kolaghan’s Command》
4:《はじける破滅/Crackling Doom》
4:《龍詞の咆哮/Draconic Roar》
2:《強迫/Duress》
1:《乱撃斬/Wild Slash》
1:《梢の眺望/Canopy Vista》
1:《燃えがらの林間地/Cinder Glade》
4:《血染めのぬかるみ/Bloodstained Mire》
3:《乱脈な気孔/Shambling Vent》
1:《燻る湿地/Smoldering Marsh》
4:《樹木茂る山麓/Wooded Foothills》
2:《吹きさらしの荒野/Windswept Heath》
1:《平地/Plains》
1:《沼/Swamp》
2:《山/Mountain》
2:《森/Forest》
2:《砂草原の城塞/Sandsteppe Citadel》
2:《遊牧民の前哨地/Nomad Outpost》
サイドボード
2:《神聖なる月光/Hallowed Moonlight》
1:《苦い真理/Painful Truths》
2:《強迫/Duress》
1:《黄金牙、タシグル/Tasigur, the Golden Fang》
1:《悪性の疫病/Virulent Plague》
2:《精神背信/Transgress the Mind》
1:《魂火の大導師/Soulfire Grand Master》
2:《光輝の炎/Radiant Flames》
1:《焙り焼き/Roast》
1:《乱撃斬/Wild Slash》
1:《炎駆の乗り手/Flamerush Rider》
実験結果
トナプラ
マルドゥメンター ○○
2構
アブザンエルドラージ ○○
青白トークン ×× 反射魔道士でブロッカー突破 ロックでダメージレース不可
8構
ブルーアブザン ○×○ アナフェンザから反射魔道士
4cラリー ○○
アブザンアグロ ○○
提案法の有効性が示唆された。
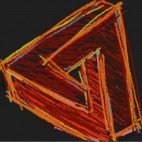
コメント